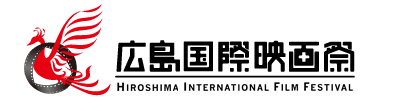金子監督の長編第1作『アルビノの木』は世界9か国の映画祭で20の賞を受賞し、第2作『リング・ワンダリング』は第52回インド国際映画祭で最高賞に輝きました。今回上映された『光る川』は3作目となる長編で、スペインの日本映画祭においてユース審査員最優秀長編映画賞を獲得。17~25歳の若い審査員11人が全出品作の中から最高評価を与えたといい「上映後に若い人たちがキラキラした目で話しかけてくれたのが忘れられない」と、海外での手応えを振り返りました。
背景には、日本映画やアニメへの関心の高まりもあるといいます。世界的に日本のアニメが観られるようになったことで、「日本文化をよく知っている、もっと知りたいという若い世代が増えている」と実感を語る一方、『光る川』ではCGを一切使わず、人間の手仕事と自然のままの姿を徹底して描きました。「AIで何でも作れてしまう時代だからこそ、生の実感を届けたい」と、アナログな制作姿勢にこだわりました。
物語の舞台は岐阜県の長良川流域。原案となったのは、地元出身の作家・松田悠八氏による小説『長良川スタンドバイミー1950』で、1950年代の少年時代の記憶を綴った私小説的な一冊です。そこに長良川流域に伝わる民話や伝承、木地師(きじし)=山中で器を挽く職人たちの歴史を織り込みながら、映画独自の物語へとふくらませました。映画に登場する木地師と里の娘の悲恋譚も、各地に残る「椀貸し伝承」や、盲目の芸人女性と里の男のかなわぬ恋を描いた岐阜の民話などから着想した“オリジナル民話”だといいます。
ロケはオール岐阜県。脚本執筆の前段階から、金子監督は長良川の源流から河口まで約200キロを縦断し、多くの支流も含めて100か所以上の候補地を歩きました。「どこかで直感的に『ここで物語が撮れる』と思う場所がある。最初に惹かれた土地は、最後までロケ地候補に残る」と語るように、土地の空気や水の色から物語を立ち上げていくのが監督のスタイルです。

本作の美術監督は、当映画祭の代表でもある部谷京子が務めました。空き家だった少年・ユウチャの家を生活感あふれる空間へと作り込み、木地師たちが暮らす山の小屋は、標高800メートルほどの広葉樹林の中に、現地の木を伐り出して一から建てました。部谷さんは図面づくりから場所選び、建設までほぼ1か月間山に通い詰めたといいます。撮影は2023年9月、実質2週間のタイトなスケジュール。台風シーズンと重なり「2、3日つぶれたら撮り切れない」という状況で、スタッフ一同、作中の少年さながらに「台風が来ませんように」と祈りながら撮影に臨みました。結果として一度も直撃を受けず、満月の夜の印象的なシーンも無事に収めることができました。
作品の核となるのが、木の器作りの手仕事です。金子監督は過去作『アルビノの木』でも木の職人を描いていますが、今回は昔ながらの“手引きろくろ”を再現するため、ドキュメンタリー作家・姫田忠義監督の『奥会津の木地師』を「バイブル」として研究。さらに、古い工法で家の改修を行う大工、山中でチェーンソー一本で木を倒す“特殊伐採”の職人など、映画業界外のプロフェッショナルを多数招き、リアルな所作と仕事ぶりをスクリーンに刻みました。
映像面では、長良川の深い青と山の緑をいかに表現するかが大きなテーマとなりました。フィルムルックに詳しいカラリストとともに事前テストを行い、かつてのフジフィルムが得意とした“日本の青と緑”に近づける色設計で仕上げたといいます。観客からも「川の青さが忘れられない」との声が多く寄せられました。

キャスティングも高い評価を集めています。ヒロイン・お葉を演じる花村明日香さん、少年ユウチャ役の有山実俊さんはオーディションで選ばれました。「この二人以外は考えられなかった」と監督が語るほど役柄に重なり、特に7歳での過酷な撮影を最後までやり遂げた有山さんの集中力と感の良さに舌を巻いたといいます。お葉が髪を切る重要な場面は、花村さん自身が実生活で髪を切った経験から発想したもので、「当時の里の女性にとって髪は宝物。それを捨てる覚悟と、山で生きる木地師の価値観の違いを込めた」と演出意図を明かしました。木地師の女性を演じた石川さゆりの複雑な表情について尋ねる観客もおり、細部へのまなざしの深さがうかがえました。

安田顕さん、堀部謙介さん、根岸季衣さん、渡辺哲さんらベテラン勢が脇を固めることで、「若い二人と少年の物語に説得力が生まれた」と監督。音楽は細田守作品でも知られる高木正勝さんが担当しました。兵庫の山中に暮らす高木さんは、鳥や虫、カエルの声が入り込む自宅で演奏を録音するスタイルで知られ、本作でも自然の息づかいに溶け込む静かな音楽が物語を支えています。「強く主張しすぎず、映画に寄り添う音楽をお願いした」という通り、控えめながらも印象に残るスコアが観客の心を捉えていました。 トークの終盤、金子監督は「自然の中での撮影は確かに厳しいが、生きて帰るために皆が助け合い、団結していく。その感覚が好きだ」と語り、CGやデジタル技術では得られない“生の手応え”へのこだわりを改めて強調しました。また、今月8日に最新作となる長編第4作『ポール・サーティーン』がクランクアップしたことも報告。現在編集作業の真っ最中で、来年初めの完成後に映画祭上映を経て国内公開を目指すと明かし、「2027年の広島国際映画祭にも、また新作を持って戻って来られたら」と再会を約束しました。
盛りだくさんのトークは拍手の中で締めくくられ、司会を務めた映画コメンテーターの鈴木由貴子さんが「『光る川』と次回作を続けて観ていただけたら」と呼びかけました。観客からは「何度でも観たくなる」「今日で三度目だが、監督の話を聞いてまた見返したくなった」といった声も上がり、手仕事と自然、人間の記憶を静かに照らす一本が、広島の夜に余韻を残しました。